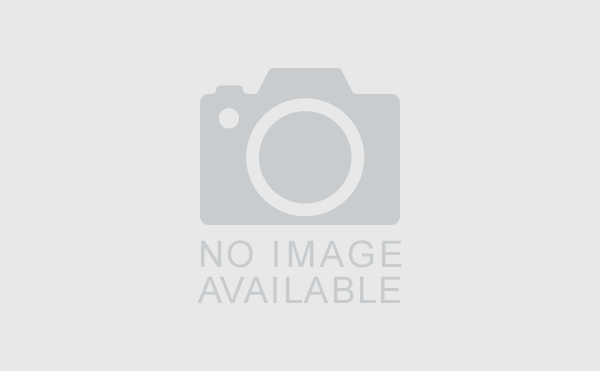日本の伝統文化解説シリーズ⑨「七福神」
日本の伝統文化シリーズ⑨「七福神亅
インドの古代宗教、ヒンドゥー教、仏教、道教、神道から様々な神・仏を集め、福をもたらすものとして、日本人に信仰されてきた。七つの幸福を授けられ、七つの厄災が取り除かれる、とされる。
枕の下に七福神の乗った宝船の絵を入れておくと、お正月によい初夢が見られる、と言い伝えられ、七柱それぞれの社を順に回ってお参りすることを「七福神めぐり」という。
七福神としてのユニット成立は室町時代末期といわれる。江戸時代に民衆の間に広まった。
・毘沙門天:ヒンドゥー教の神が仏教の四天王の一つとなった。
・大黒天:ヒンドゥー教の最高神のシヴァが大国主命と一体化。財産の神様。
・弁財天:紅一点。古代インドの河の神が宗像大社の祭神であるイチキシマヒメノミコトと一体化。
・寿老人と福禄寿:道教の仙人で、長寿をもたらすとされる。福禄寿は長い頭が特徴。
・布袋和尚:唐の時代の禅僧(実在したといわれる)。大きなお腹とニコニコ笑顔が特徴。
・恵比寿:イザナギ・イザナミの子で、唯一の純和製。商売繁盛や五穀豊穣をもたらす。
「子どもたちにつなぐ日本文化の会」(←クリックorタップ)を仲間とともに立ち上げました。
3/12・13にイベント開催予定。
・なるほど!講座「日本の伝統文化」
・ワークショップ:味噌玉を作ろう
・お抹茶コーナー(和菓子とともに)
詳細はこくちーず(←クリックorタップ)で。ご興味のある方は、ぜひ覘(のぞ)いてみてください!