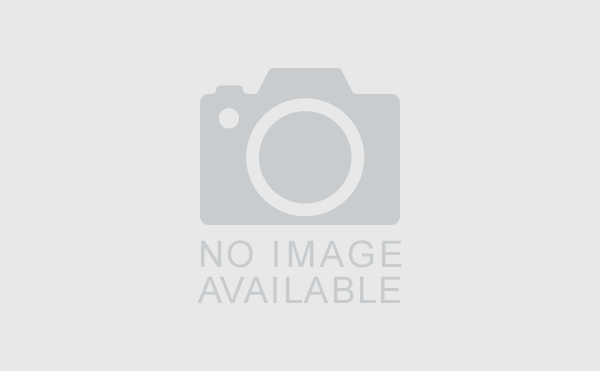小中学生向けの経済講座 第73回
12月20日(月)、小中学生向けの経済講座(第73回)を開催しました。
今回の主な内容
①この1年を振り返って
②今日のテーマ:日本の紙幣の印刷技術
③紹介記事
①この1年を振り返って
本日が2021年最後の経済講座だったので、今年はどんな1年だったか尋ねてみました(※経済とは関係なく)。
SさんもK君も「学校が楽しくてよい1年だった」と、同じ内容の返答。二人とも中学1年で、中学に入学したこと自体が大きな出来事です。新しい友達ができたこと、クラスや部活などの楽しさを口を揃えて語ってくれました。
とても嬉しくなって、思わずたくさん質問してしまいました。
※大変残念なことに、I君は体調不良でお休みでした。
②今日のテーマ:日本の紙幣の印刷技術
前回に続き、阿部泉『お金の歴史』(清水書院)を活用させていただきました。
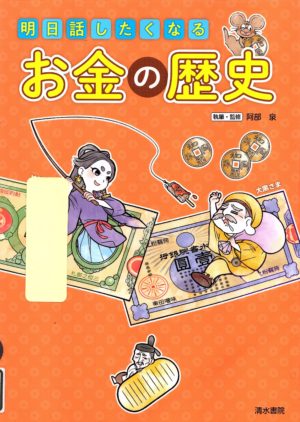
日本のお札を、アメリカやイギリスのお札(実物)と見比べながら、その精巧な作り・高度な印刷技術を堪能しました。まさに「職人の技」です。
③紹介記事
1枚目はこちら。

記事中のグラフから読み取れることを指摘してもらいました。このようなグラフは変化(ここでは折れ線グラフの形状)に目が行ってしまいますが、それだけでなく、横軸と縦軸の数値にも着目し、数量分析することが必要であることをレクチャーしました。
※僕はかつてはこのグラフを作る側にいました。
2枚目はこちらです。

この記事についても、グラフを活用し、自分が経営者だったら、グラフ内のどの部分に注目するか、考えてもらいました。一番数値の大きいところに目が行きがちですが、そこは誰でも見ます。世の中の全員を対象にするわけではありませんから、「一定のまとまった層」としてどのような人たちがいるのかを詳細に考察することが必要です。
これで2021年の経済講座全日程が終了しました。皆さん、次回までに「お年玉」という、非常にユニークな経済現象(海外に似たような習慣はゼロではないが極めて少ない)をお楽しみください。